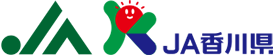監修 堀井ヒロ
材料(10人分)
| 米 | 5合 |
|---|---|
| 水 | 6合 |
| もち米 | 5合 |
| 水 | 4合 |
| 酒 | 大さじ4 |
| しょうゆ | 大さじ4 |
| 塩 | 小さじ2 |
| 砂糖 | 小さじ1 |
| ワラビ(ゆで) | 200g |
| タケノコ(ゆで) | 200g |
| ニンジン | 1本 |
| 鶏肉 | 200g |
| シイタケ | 5枚 |
| ゴボウ | 1本 |
| サヤエンドウ(またはグリーンピース) | 少々 |
作り方
- ワラビ、タケノコ、ニンジン、シイタケ、ゴボウ、鶏肉は、それぞれ小さめに切る。
- 鍋に少々の油を熱し、(1)を入れて炒め、砂糖と醤油で薄味をつける。ザルに上げ、煮汁を切っておく。
- 米を洗って炊飯器に入れ、分量の水を加え、調味料と(2)を入れ、混ぜて炊き、10~15分蒸らす。
- (3)を飯盆にとり、しゃもじで切るように混ぜる(水分をとばす)。塩ゆでしたサヤエンドウを散らす。
※もち米とうるち米を混ぜて炊くときの水の計算は
もち米×0.8+うるち米×1.2
(野菜の量によっても水加減をする)
※手軽に作れるように炊きおこわにしました。
山野の幸で
身体の内から感じる
春のおとずれ。
雨が降ると春雨といい、風が吹けば春一番といって、待ちに待った春の到来を喜びます。
桃の硬い蕾つぼみがほころびる頃になると、やっと寒さから解放され、山野では蕨わらびが一斉に芽を出し、土手には土つく筆しが頭を揃え、蓬よもぎは一段と青さを増します。やがて筍たけのこもあちこちに顔を見せます。
山菜や春の野菜は、昔から「春苦味」といわれ、苦味の元であるアクが体を刺激し、胆嚢の働きを活性化して調子を整え、すっきりした体にしてくれます。春が来て野山が目覚めるように、人の体も冬の眠りから起こしてくれるのです。
料理に使う山菜は、比較的長期間採取できる蕗ふき・蕨・筍・蓬などを上手に保存しておけば、年中時期を問わず楽しむことができます。また、山菜ではありませんが、この時期に桜の花や葉を漬け込んでおけば、春の香りをいつでも味わえます。以前、「ちゃぼの葉だんご」を包む「サンキライ」の葉を加工保存し、次の旬が来るまで使うことも紹介しました(2002年8月号)。
三豊郡財田町「たからだの里」加工部会長西川幸子さんのグループでは、道の駅に「たからだおこわ(山菜おこわ)」を出しています。春には春の山菜を、秋には銀杏や栗などを採取保存し、常に旬の味を味わえるようにしているそうで、「この山菜おこわを目当てに、遠くから多くの人が訪ねてくれるのが非常に嬉しい」と話されています。
郷土料理は、とれたての魚やもぎたての野菜などが入手しやすく、美味しい料理を作る機会に恵まれている風土と、長年蓄積された人々の知恵と心づくしが生み出したものであると思います。